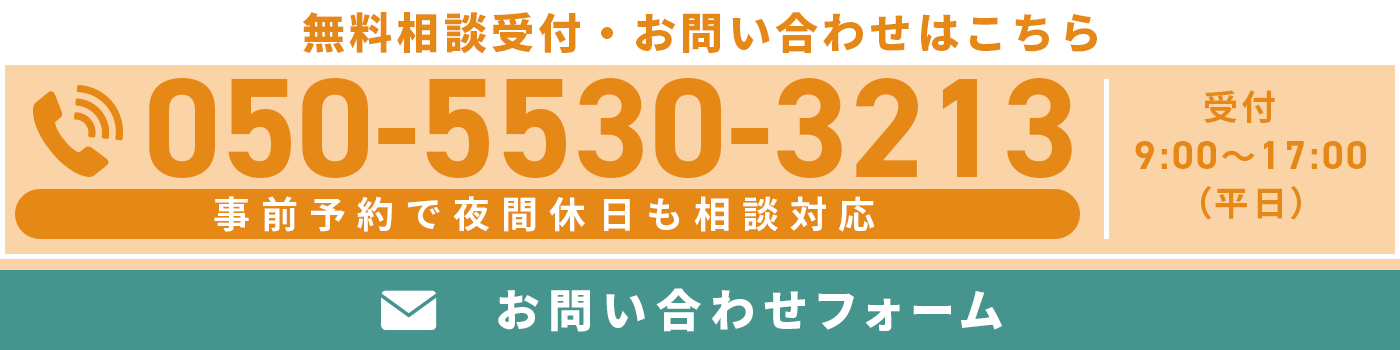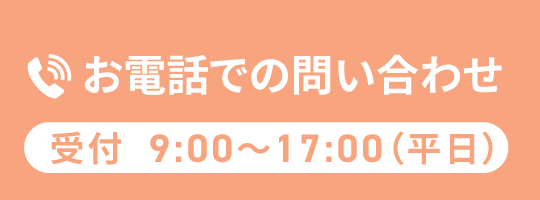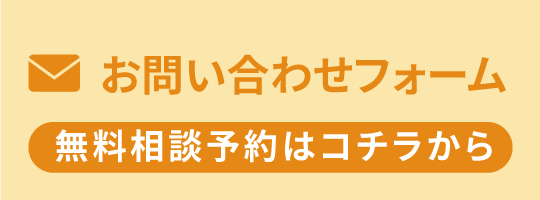自筆で書かれた遺言書を預かっていた、もしくは亡くなった方のご自宅等から発見したという場合には、その遺言書を家庭裁判所に提出し、検認という手続きをしなければならないと定められています。
検認というのは、その遺言書が確かに亡くなった方によって書かれたものであるか否かを確認する作業です。
自筆で書かれた遺言書は、この作業を終えないと遺言書として使用することができませんので、まずはここから手続きが始まることになります。
検認の流れ
検認手続きの申立て
亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、検認手続きの申立てをします。
検認の際には、相続人全員が立ち会うことになっていますので、誰が相続人であるかということを証明するための書類を添付することになります。

裁判所からの電話連絡
裁判所は申立てを受け付けた後、書類の確認し、日程調整のために申立人に電話連絡をします。
本来は相続人が全員集まるのが好ましいのですが、少なくとも申立人が出席してくれないと始まらないため、申立人の都合を聞かれます。
日程調整後、家庭裁判所から相続人全員に宛てて日程の通知が送付されます。

検認当日
検認当日は、忘れずに遺言書を持参してください。
この際に注意していただきたいのが、封筒に入っている遺言書は開封してはいけないという点です。
誤って開けてしまうと、罰則もありますので、必ず裁判所で開けてもらうようにしてください。
時々、複数の遺言書が見つかることがありますが、その場合にはすべての遺言書を持参するようにしてください。
複数の遺言で内容が矛盾してる場合には後の日付のものが有効になるのですが、開けてみるまでは分からないからです。
検認は内容の可否などを確認する手続きではないので、遺言書を開封して「これはお父さんの書いたもので間違いないでしょうか?」などと簡単な確認をされるだけなので、裁判所の手続といっても緊張する必要はありません。
検認が完了すると、遺言書に検認証明をつけてもらえます。
ここまでの手続きを経ることで、自筆の遺言書が遺言書として使用できる状態になります。
自筆による遺言書の注意点
検認によって自筆の遺言書は遺言書として使えるようになるのですが、いざ使おうとしても使えないケースが、かなりの割合で存在します。
その理由は、書き方が間違っていることがあるからです。
家庭裁判所での検認は、あくまで故人本人によって書かれたものであるか否かの確認作業であって、法律で定められた要件を満たしていることを保証してくれるものではないのです。
使えない遺言書の例
- 日付、氏名、押印のいずれかがない
- 遺言者の住所の記載がない
- 財産がはっきりと特定できていない
- 財産をどうしたいのかが曖昧
順番に解説していきます。
① 日付、氏名、押印のいずれかがない
まず①ですが、自筆で遺言を書く場合、日付を書くこと、氏名を書くこと、印鑑を押すことが法律ではっきりと要件とされてしまってるため、例えば筆跡で誰が書いたか判別できる場合であっても、氏名の記載がなければ無効になってしまいます。
② 遺言者の住所の記載がない
次に②ですが、住所は法律上は必要事項とされていませんが、世の中には同姓同名の方がいますので、実務上は記載がないと使えません。
封筒に入った遺言書を検認してみたら住所の記載がなく、「夫である○田×男に全財産を~」という記載に注目して「住所の記載はないが戸籍とセットにすれば遺言者個人の特定は可能ではないか?」と法務局にかけあってみた経験があるのですが、法務局からの回答は遺言書単体で個人が特定できなければ遺言としては使用できないというものでした。
一部の金融機関はこの遺言を使って手続きができたのですが、最終的には他の相続人に協力してもらって遺産分割協議書を作成し、なんとか登記は申請することができました。
他の相続人に協力していただけたからよかったものの、認知症の方や金銭を要求される方がいたら大変なことになるところでした。
実はその遺言は生前にご夫婦で他の専門家に相談して作成されたものだったそうですが、法律上の要件と実務上の要件は必ずしも同じではないという落とし穴にはまってしまったことになります。
③ 財産がはっきりと特定できていない
④ 財産をどうしたいのかが曖昧
そして③④ですが、これらはまとめてご説明します。
どんな遺言書も、最終的には第三者(金融機関や法務局など)に読んでもらうために作られています。
ですから、誰が読んでも同じ解釈になるような書き方をしてもらわないと困る、ということになるのです。
例えば③については、複数の不動産を所有されていた方が「自宅は長男に、その他の不動産は長女に~」という遺言を書いた数年後に自宅を壊して賃貸マンションに引っ越してしまい、不動産が特定できないという理由で登記ができなかったケースがあります。
また、④についてですが、口頭なら伝わることも文書にすると不明瞭になることがあります。
遺言書というのは、主に「誰に何を承継させるか」を指示するための書類です。
例えば生前に子どもたちに集まってもらい、お父さんから「お前たちにはなるべく同じように財産を渡したいから、一郎には○○町のアパートを、花子には××町のアパートを任せたい」という話をしたなら、これはそれぞれにアパートを相続させるという意味にとらえられるでしょう。
しかし、遺言書に「一郎には○○町のアパートを、花子には××町のアパートを任せたい」とだけ書かれていても、単に修繕や家賃の管理を任せるつもりだという風にも読めてしまうのです。
ですから、相続人に対しては「相続させる」、場合によっては「遺贈する」、相続人でない人には「遺贈する」というストレートな書き方をすべきなのです。
自筆の遺言書が使えない場合の対応
自筆の遺言書が登記や銀行口座の解約に使えない場合、取りうる手段は次の二つとなります。
① 遺産分割協議をする
使えない遺言書であっても、意味がまったく通らないようなものは稀です。
可能であれば、相続人の間で故人の遺志を尊重しながら遺産分割協議をするのが理想的であるといえます。
遺言の内容が遺留分を侵害していた場合、分割協議を通じて調整してしまえばよいでしょう。
相続人の間で話がまとまらなかったり、協力が得られない場合には調停や訴訟をすることになります。
② 訴訟する
遺言自体は成立しているのに、内容の解釈などについて争いがある場合で話し合いがまとまらないときは、裁判によって「この遺言が言いたいのはこういうことであるはずだ」という主張をしなければなりません。
なお、使えない遺言書の例①でご紹介した不備がある場合、遺言書が完全に無効なので、内容の解釈で争う余地はありません。